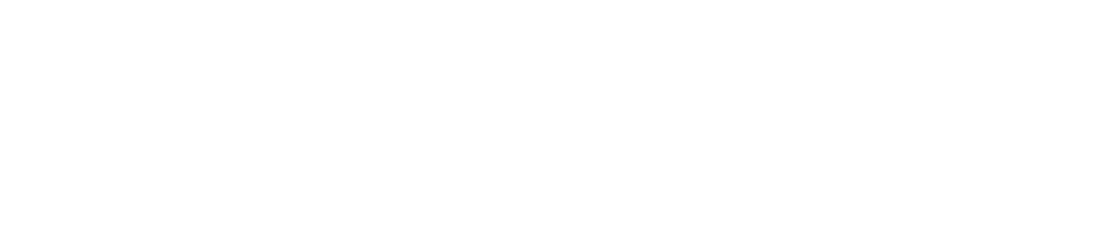遺言とは、人が自分の死亡後に、法律上の効力を生じさせる目的で、民法上の一定の方式に従ってする単独で自由に行う意思表示です。もし、遺言がないときは相続人同士での遺産分割協議をして誰が何を相続するかを決めることになります。
遺言書作成サポート —遺言の重要性
遺言の目的の主なもの
親族同士の争いを避ける
相続財産が、現在、家族が住んでいる不動産のみだった場合、不動産は、簡単に売却、分割できません。また、現在住んでいる家族も行き場を失いかねません。そんな時、相続人ひとりひとりに配慮した方策を考え、遺言として思いを残すことで、相続を円滑に進める事が可能となり、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。
自分の人生を振返り大切な人への思いを伝える
遺言は、人がひとりで自由に行う意思表示です。ですから遺言を書くことで、自分の人生を振返り、夫や妻、子供たち、また兄弟姉妹や支えてくれた人達を思い起こす良い機会です。例えば、介護してもらった相続人以外の長男の嫁や事業を手伝ってくれた子供、兄弟へ相続分を増やす、遺贈する等、自分の特別な感謝の思いを残すことができるのです。
遺言は特別なケースの人たちがするものではありません
◦不動産を所有し相続人が複数いる方
◦相続人以外の人へ財産を譲りたいと考えている方
◦法定相続以外の割合で相続させたいと考えている方
◦独身で相続人がいない方
などは遺言を書くことをおすすめ致します。
遺言出来る人
遺言は、人が死後に向けて行う最後の意思表示で、一人で行うものです。ですから、いくら仲が良いからと言って夫婦共同で遺言することは、できません。共同遺言は、無効となります。また、遺言者には、意思能力が必要とされ、心身喪失・泥酔状態の時には遺言はできません。
民法では、満15歳以上であれば法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意がなくても単独で有効な遺言が出来るとされています。
成年被後見人でも、本心に復した時、すなわち正常な判断能力が回復したときは、医師2人以上の立会のもとで有効な遺言をすることが出来ます。
被補助人・被保佐人は、補助人・保佐人の同意を得なくても、単独で有効な遺言をすることができます。
遺言能力のない者がした遺言は無効です。ただし、遺言能力は、遺言をするときに備わっていれば良いので、その後判断能力がない状態になったとしても、遺言の効力に影響はありません。
遺言で出来ること
法律的に効力が生じる事項は民法で決められています。
相続に関する事項
◦相続分の指定及びその委託
◦遺産分割方法の指定及びその委託
◦遺産分割方法の指定及びその委託
◦遺留分減殺方法の指定
相続以外の遺産の処分に関する事項
◦遺贈
◦信託の設定
身分上の事項
◦認知
◦未成年者後見人・未成年者後見監督人の指定
遺言執行者の指定およびその委託
祖先の祭祀主宰者の指定
生命保険金の受取人の変更(平成22年4月保険法施行により)
寄付行為
相続人廃除、及びその取消
特別受益者の持戻し免除
共同相続人間の担保責任の指定
上記以外のことを書いても法律的効果や強制力を生じることはありません。しかし、付言事項として遺言者が、相続人や大切な人に対して、気持ちを表し書き残すことは大変効果が大きいのです。
遺言書にはどんなものがある?—遺言の種類
普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
特別方式(一般危急時遺言・船舶遭難時遺言・伝染病隔離者遺言・在船者遺言)
以上の遺言の中で一般的に使われているものが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
いつでもどこでも字の書ける人であれば簡単に出来る遺言です。しかし、変造や破棄の恐れ、また発見されることなく時間が経ってしまうなど保管に注意が必要です。また、方式が不備で無効になることもあります。さらに、家庭裁判所で検認を受けなければ相続手続に利用できません。
【作成手順】
①全文を自筆で書く(ワープロや代筆は×)
②日付を書く(○月吉日は×、例えば10月7日と書く)
③署名をする(氏・名の両方)
④印を押す(実印でなくても良いが、シャチハタは×)
公正証書遺言
遺言者が、遺言に書きたい内容を口で伝えて、公証人が公正証書に作成するものです。
◦原本が公証役場に保存され、正本1通は、遺言者にわたされます
◦公証人が作成するので無効になることはなく、変造・紛失・隠匿の恐れがありません
◦公正証書遺言を作る為に必要な書類や資料を整えなければなりません
◦証人2人の立会が必要です
◦家庭裁判所での検認が不要で、相続発生後、すぐに相続手続に入ることができます
遺言執行者
民法では、遺言の内容を実現するために、遺言執行者をおくことができるとされています。相続人の中の誰かが、遺言の内容を実現しても問題はありません。しかし、遺言の内容を実現するにあたり、円滑に事が運ばない内容があるときは、遺言書の中で遺言執行者を指定しておく必要があります。例えば、認知や廃除・廃除の取消には、必ず遺言執行者が必要となります。相続人間に利害関係の対立がある場合も、遺言執行者を指定しておいたほうが良いでしょう。遺言書に遺言執行者の指定がないときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができます。
【遺言執行者は】
◦相続人の代理人とみなされ、遺言者の意思を実現・実行する役目を負います。
◦未成年者や破産者は就任することができません。
◦就任後、遺言書の検認申立(自筆証書遺言の場合)、財産目録を作成、財産の管理・その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。
※相続人は、相続財産を処分したり、執行を、妨害することはできません。
【遺言で相続人以外の第三者に不動産を遺贈する場合】
◦遺贈された不動産の相続登記をする場合には、法定相続人の実印・印鑑証明書が必要です。
◦遺言執行者を指定しておけば、受遺者が単独で法定相続人に対して交渉するよりも、手続を円滑に進めることができます。
検認
公正証書遺言以外のすべての遺言(自筆証書遺言と秘密証書遺言)は、家庭裁判所での検認が必要となります。遺言書の保管者(保管者がいない時は遺言書を発見した相続人)は、遺言者の死亡を知った後、すみやかにその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認をうけなければなりません。
検認とは、遺言書が後で、偽造・変造されるのを防止し、その保存を確実にするために遺言書の形式・態様などを調査し、状態を確認する手続です。遺言の執行に先立っておこなわれる証拠保全手続です。検認手続が終了しないと、実務上の遺言執行(金融機関の名義変更等)ができません。
家庭裁判所に遺言書の提出を怠り、その検認をしないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で封印されている遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。
【検認に必要な書類】
◦遺言者の原戸籍謄本・除籍謄本
◦相続人全員の戸籍謄本と申立人の戸籍謄本
専門家に相談しましょう!
行政書士・相続FPは、公正証書遺言作成に必要な資料を集め整えます。また、公証役場との折衝も行います。遺言の内容の中身については、公正証書遺言にする前に検討して決めなくてはなりません。
その遺言書原案作成の際のご相談に応じサポートいたします。証人となることもできます。
遺言を作成した方は、みなさんほっとした表情になられます。今まで、心の中でやらなくてはいけないと、ずっと思い抱えていた肩の荷をおろされたからではないでしょうか。
遺言はあなたの第2の保険です。のこされた大切な方の為に遺言を書きましょう! お問合せはこちらから
当ホームページの作成には細心の注意を払っておりますが、法令の変更に対処できない場合もあり完全性を保障するものではありません。また状況によっては当てはまらない場合もあります。当サイトの情報利用により生じた直接・間接の損害に対して当管理者側は一切の責任を負いません。自己責任においてご利用ください。